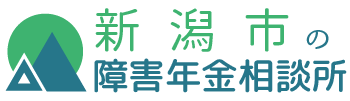精神障害、発達障害で障害年金請求する手続きのポイント
(うつ病、統合失調症、双極性障害、自閉症スペクトラム症(ASD)、注意欠如多動症(ADHD)など)
<1>初診日
①初めて医療機関を受診した日を初診日と言いますが、精神障害、発達障害の場合、障害認定日や請求時の病名と、初診日の病名が違うことが多いです。
障害年金請求手続きでは、病名が違っても相当因果関係がある病名の場合は、病名が変わる前に受診した医療機関の初診日が初診日になります。
(例)適応障害、その後、うつ病に病名が変わった場合、適応障害で受診した医療機関の初診日が初診日になります
適応障害~うつ病、その後、発達障害が見つかった場合、発達障害で請求する場合でも、適応障害の初診日が初診日になります。ただし、発達障害の場合、幼少期まで遡って、医療機関に受診したことがないか、確認する必要があります
②最初内科を受診して、その後、精神科や心療内科を受診した場合は、内科の受診が初診日になります。
(例)激しい動悸がして内科を受診したが、異常は見つからず、精神科を受診したら、パニック障害と診断され、その後うつ病を発症した場合、内科の受診日が初診日になります。
③医療機関以外の機関から精神障害や発達障害の疑いを指摘された場合は、その後に受診した医療機関の初診日が初診日になります。
④発達障害でも医療機関を初めて受診した日が初診日になります。ただし、先天性の知的障害の場合は産まれた日が初診日になります。
<2>障害認定日
障害認定日は、初診日から1年6ヶ月経過した日になります。ただし、20歳になる日の1年6ヶ月以上前に初診日がある場合は、20歳の誕生日の前日が障害認定日になります。
障害認定日時点で、障害年金受給できるくらいの状態であれば、この時点で受給権が発生します。
障害認定日で障害年金を請求する場合は、障害認定日~3ヶ月以内の現症日の診断書が必要です。ただし、20歳時点が障害認定日の場合は、20歳になる3ヶ月前から20歳になった後3ヶ月以内の現症日の診断書が有効になります。
<3>対象の病名
国民年金や厚生年金の障害年金は、精神病でも神経症や人格障害に分類される病名は対象外になります。
こちらをご覧ください。
ただし、労災保険の場合は、神経症も対象です。
<4>障害年金受給できるレベル
障害年金の等級ですが、国民年金の場合、1級、2級 厚生年金の場合、これに加えて3級が受給できます。
このレベルですが、
3級・・・フルタイムで仕事ができない、仕事ができても短時間で単純作業
2級・・・仕事ができない、ただし、見守りがあり、相当配慮されている状態なら仕事ができる
介助無しで日常を送れない、原則一人暮らしはできないが、福祉サービスを利用しながら一人暮らしができている
1級・・・閉鎖病棟などで生活している 全介助状態